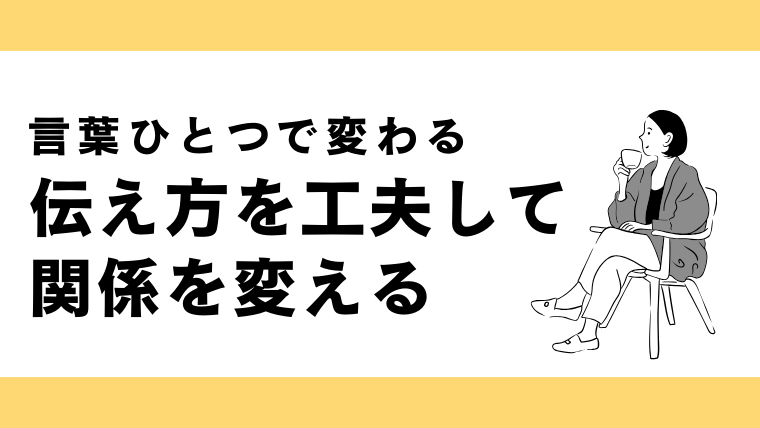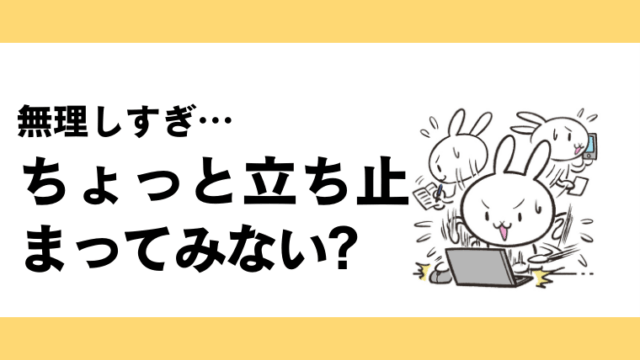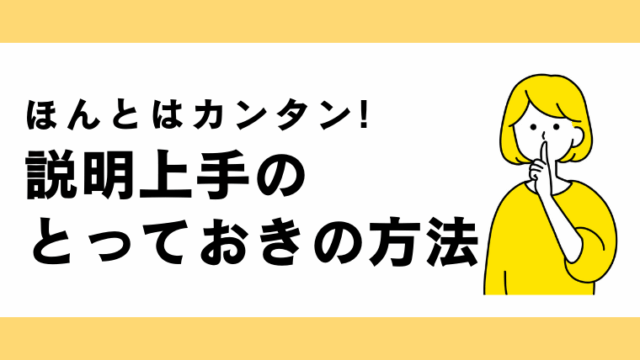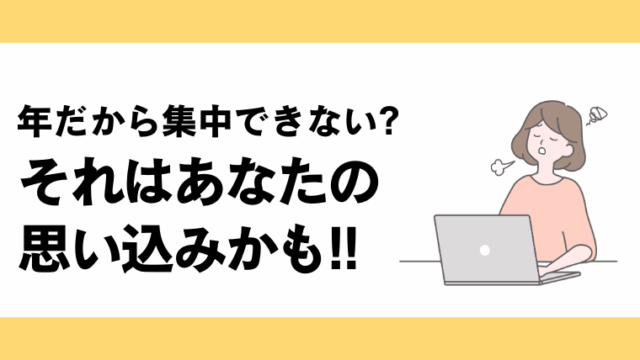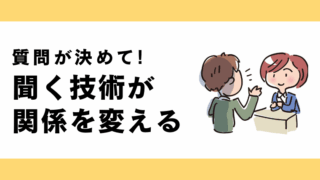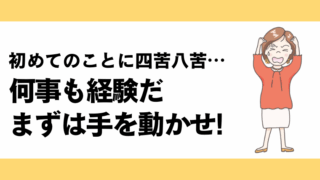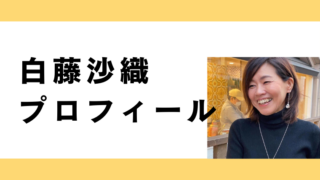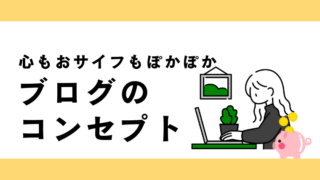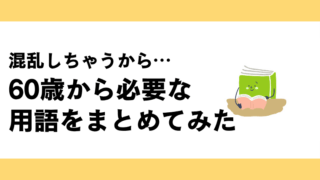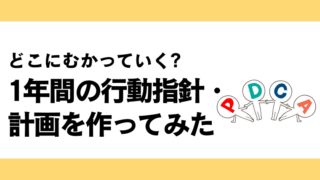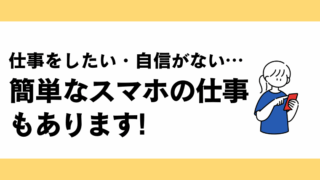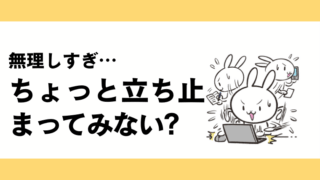管理職になったばかりの頃は、雰囲気がよく活気のある職場にしたいと希望に燃えていたのに…。
気づけばチームの士気が落ちて、空気も重く感じてしまう。
「雰囲気が悪いのは、自分のマネジメントが悪いせい…?」
「いや、部下が言うことを聞かないから…?」
そんなふうに、自分と相手を責める気持ちの間で揺れていませんか?
管理職になると、いろいろな葛藤が生まれますね。
そして、どうにかしようと改善にむけて行動しているからこそ、この記事を開いてくださったのだと思います。
そんなあなたにこそ届けたいのが、
「相手の抵抗を生まずに、あなたの話を自然と聞いてもらえる方法」。
実はこの方法、心理療法の現場で使われている「ことばの技術」なのです。
相手の心にやさしく届き、無理なく動きたくなるような「伝え方のコツ」をぜひお読みください。
ちょっと難しく聞こえましたか?
でも大丈夫です。すぐに読み通すこともできますし、あとでゆっくり読んでいただいても構いません。人は変化の中で自然と学べるものだから。
こんにちは。
札幌でWebディレクターをしている、白藤沙織(しらふじさおり)です。
私は30年以上企業で働いてきて、人間関係やマネジメントに試行錯誤をしてきました。
そんな経験から、すべての働く人が笑顔になれることを目指して発信をしています。
今日は、組織のビジョンや目標を共有したり、方向性を話すときにとても役立つ、静かに効くことばの使い方をお届けします。
心理療法家「ミルトン・エリクソン」が治療に使っていた「ミルトン・モデル」という言葉で、私は「ミルトン・エリクソン」を知って、精神的にラクになった経験があります。
言葉ひとつで、雰囲気が良くなることも、悪くなることもある

Web屋の私がなぜ心理療法の勉強をしているかというと、管理職として組織をまとめるのに苦労していたからです。
会社の売り上げ構成を変えるために、スタッフの意識を変える必要がありました。
ところが、私が職場の雰囲気を変えたくてがんばればがんばるほど、自分が周囲から浮いてしまったんです。
どうしようもなく行き詰ってしまったときに、勉強会で声をかけてもらい心理療法の勉強もすることになりました。その中に「ミルトン・モデル」も含まれていたのです。
今思えば、「変わる必要なんてない」と思っていたスタッフに、ストレートに「変わりなさい」と言っても届くはずがなかったんです。
まず、「変わりなさい」というのは、「今のあなたではNGです」と暗に伝えているようなもの。どちらかというと、NGの方が伝わるから、抵抗を生んでしまうのです。
今の私なら、暗に「これから変わっていくことでいいことがありますよ」と伝えるような言葉がけをすると思います。
これこそが、無意識に届く「ことばのチカラ」──ミルトン・モデルなんです。
管理職のための「ことばの処方箋」:ミルトンモデルを取り入れよう

先に紹介したとおり、「ミルトン・モデル」は、アメリカの心理療法家ミルトン・エリクソンが使っていた「無意識に届く」言葉の使い方の体系です。この言葉の使い方は、実はビジネスの現場でも応用できる、たとえていうと「柔らかなコミュニケーション技法」なんです。
ビジネスの現場では、わかりやすく、はっきり伝えることが重要です。段取りや手順を説明するときには誤解を生まないので有効な伝え方です。
でも、聞く相手がどこかで不満を感じていたり、心を閉ざしていたりする時は、明確な言葉ほど跳ね返されてしまい、素直に聞いてもらえません。
対立はここで生まれるのです。
そんなときに使いたいのが、ミルトン・モデルのことばです。
それは、直接的な命令や説得ではなく、
相手の中に「動きたくなる気持ち」を呼び起こす言葉がけです。
たとえば、こんな言葉を聞いたことはありませんか?
- 「あなたのペースで進めてくださいね。」
- 「何が正解かは、人によって違いますから」
- 「まだ答えが出ていないなら、それも自然なことですよ」
よくよく考えると、あいまいな言葉ですが、聞いた人はどこかほっとしたり、自分の中から答えをみつけようとします。
ミルトン・モデルの基本
ミルトン・モデルの言葉には、いくつかの特徴があります。
ここでは、代表的な特徴を5つ紹介しますね。
- あいまいさ:言い切らない、余白を残す、文法的には判断できない
情報源は具体的に言わないで、相手の考え方や気持ちを知っているという - 間接的な表現:第三者の言葉を引用する、直接言わない
「他の人が言ってたんですが…」など、距離を置いた伝え方 - 前提:仮定と同じ
「誰でも最初は戸惑うものですよ」 - 普遍的数量詞:一般化されている、参照するものがない
「誰でもできることです」 - ダブルバインド:「または」で区切られた選択肢を与える
「AとB、どちらで進めますか?」(でもどっちも前に進む)
このような言葉がけをしていくと、直接的に「変われ」と言わなくても、相手が自分の中から「変わろう」と感じ始めるきっかけになるからです。
たとえば、部下が新しい業務に自信がなさそうなとき。
こんなふうに声をかけることができます。
「最初は誰でも手探りですよ。大丈夫です、ゆっくり慣れていきましょう」
あるいは、意見が出ない会議ではこんな風に言えるかもしれません。
「まとまっていても、いなくても構いません。思いついたことを一つ聞かせてもらえると、ヒントになるかもしれません」
言葉の力で、安心感と自発性の両方を引き出す。それがミルトン・モデルの最も効果のあることなのです。
管理職になると、正しく伝えなければ、成果を出させなければとプレッシャーを感じがちです。でも、すべてを「わかりやすく言う」必要はないのです。
これにより、ゆとりがでてきて、スタッフひとりひとりが自分たちで考える時間が増えます。
組織のマネジメントで大切なことは、メンバーが自発的に動くこと。
相手の中にある力を信じて、余白を残すほうが、チームはしなやかに動き出します。
シーン別:使える「ことばの処方箋」フレーズ集
では、ミルトン・モデルをどのように職場で活かすのか、シーン別に考えてみましょう。
会議で意見が出ないとき
参加メンバーに安心感を与え、発言を促したいときは、「意見はありませんか?」と聞くのではなく、こんな風に聞いてみてはどうでしょうか?
「まとまっていても、まとまってなくても大丈夫ですよ。思いついたことがあれば、ぜひ」
解説しますね。
-
ダブルバインド
→「まとまっていても、まとまっていなくても」
どちらをとっても、発言を促している。 -
あいまい性(曖昧な表現)
→「まとまっていても、まとまってなくても」
定義があいまい。だから安心しやすい
→「大丈夫ですよ」
何がどう大丈夫か明言していない=安心を与える -
時間の前提
→「思いついたこと」=今ここで浮かんだことでよいと言っている。
→ 「いつでもOK」の余白がある。 -
間接的な許可・肯定(ソフトな暗示)
→「ぜひ」:命令せず、やさしい推奨
スタッフの報告が遅れているとき
スタッフからの報告や相談がないとき、直接「提出してください」と言っても、「はい」と言われて提出されないのがオチ。ハードルを下げて、共有することを習慣化してみましょう。
「誰でも迷うことはあります。だからこそ、話してもらえると助かります」
解説しますね。
-
普遍的数量詞
→「誰でも」
どんな人にでもあること = あなただけではない と言っている。 -
前提
→「話してもらえると助かります」
話すことが前提となっている = 話さないという選択肢がなくなる。
自信をなくしているメンバーに
自信をなくしていること自体を否定しないで、それでもいいんですといったん受け止めることがポイントです。そのうえで、ゆるやかに自信を取り戻す方向に言葉がけをしてみます。
「まだ結果が出ていないだけで、積み上げてるものは見えてます」
解説しますね。
-
前提(時間)
→「まだ結果が出ていない」
どんな人にでもあること = あなただけではない と言っている。 -
あいまいさ
→「積み上げてるもの」
何を積み上げているのか、明確に定義していません。
技術、信頼、経験など、さまざまな解釈ができます。 -
前提
→「積み上げてるものは見えています」
将来成果がでることを前提にして話している。
指示や提案を柔らかく伝えたいとき
どんなに言葉が丁寧でも、スタッフに指示するときは命令と受け取られて反発されることがあります。柔らかく伝えてみましょう。
「この方向で進めるといいかなと思っているんですが、どう感じましたか?」
解説しますね。
-
間接的な表現
→「進めるといいかなと思っているんですが」
「進めてください」「こうしてください」とは言っていない。
言外で「否定する必要はない」「受け入れても安全」と感じさせる。 -
あいまいさ(主語)
→「思っているんですが」
自分の考えを主体にしているけれど、あくまで「思っている」であって、「決めた」ではない。 -
前提
→「どう感じましたか?」
「どうしますか?」ではなく、「どう感じましたか?」という問いかけで、選択を迫るのではなく、「感じたことを自由に言っていい」という前提になっている。
チームが疲弊しているとき
たとえば、繁忙期で残業が続いたときなどに、スタッフの緊張をほぐし、ねぎらうときにも応用できます。
「たくさんやってきましたよね。今はちょっと休んでも大丈夫です」
解説しますね。
-
前提
→「たくさんやってきましたよね」
「あなたは頑張ってきた」という認知と承認が含まれている。
たくさんやったことは事実なので、「すでに頑張ってきた」ことを否定できない構文になっている。 -
あいまいさ(肯定)
→「今はちょっと休んでも大丈夫です」
具体的にどのくらい休んでいいかは伝えていない。聞いた人が無意識で、自分に合った時間を選択できる。 -
前提
→「今はちょっと休んでも」
「今は」は一時的な状態を示している。この瞬間に必要なのは休みだということが受け止めやすい。
まとめ:もう少しだけがんばろうと思うあなたへ

いかがでしたか?
「ものごとを正確に伝えよう」、「指示通りに動いてもらおう」ということにフォーカスしすぎると、組織に緊張感が生まれます。また、指示するあなたが「厳しい人」「きつい人」との評価も受けやすくなります。
ですので、発言の中にミルトン・モデルを使ったフレーズを溶け込ませると、ちょっとした余裕が生まれます。
そのためには、ミルトン・モデルのフレーズは、ゆっくりと低めの声でいうこともポイントです。
【課題です】
ミルトン・モデルを使って、ご自身に優しく声をかけるとしたら、何と言ってあげたいですか?
組織を変えようとがんばってきて、もう少しがんばってみたいあなただから、最初にほっとひと息ついてもらいたいなぁと思っています。
大丈夫です。あなたはもうできます。
そして、今日紹介したフレーズの中から、ひとつだけでも使ってみてください。
あなたの言葉が、誰かの心をそっと動かす日が、もう始まっています。