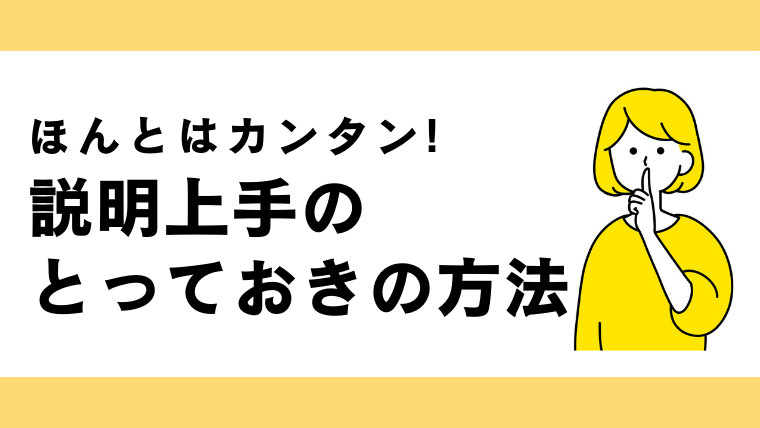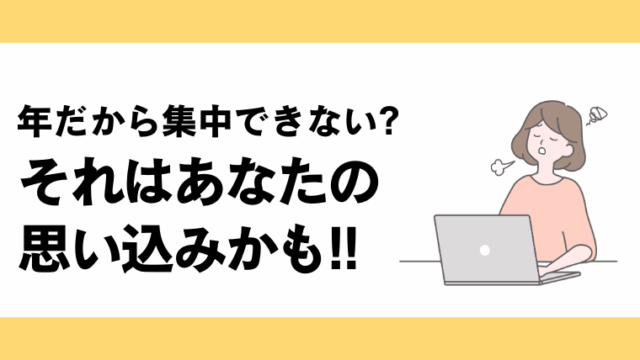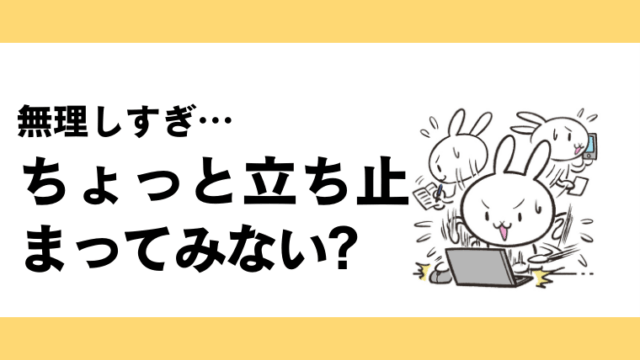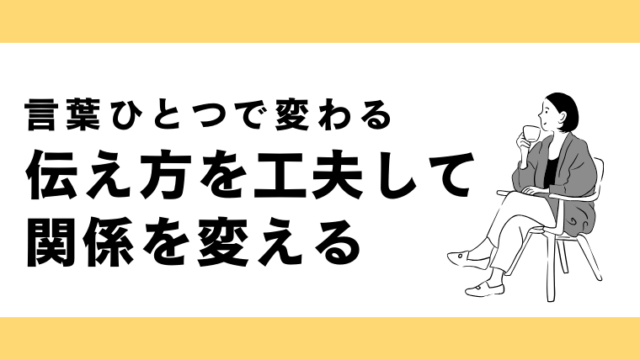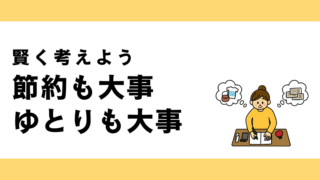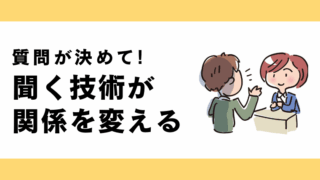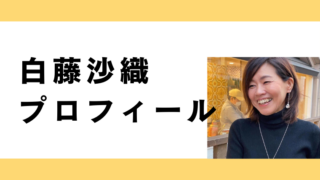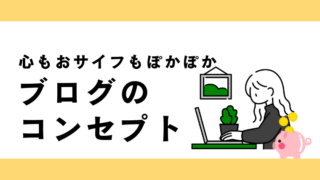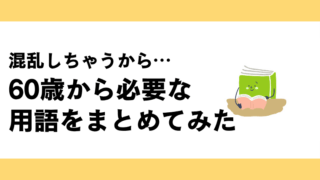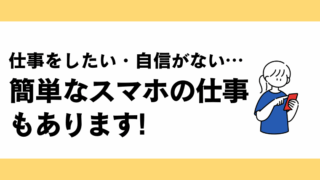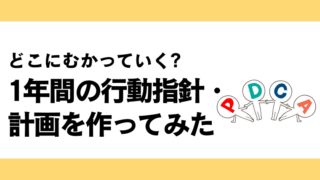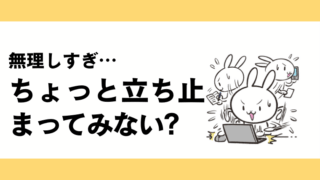念願かなって管理職になったのに、部下との関係があまりうまくいかず、自分の仕事にも影響が出ている。
指示が伝わっていない感じがするし、「私の話をちゃんと聞いているのか」と不安になることもある。
こんな経験はありませんか?
解決策はないかと、説明上手になるためにいろいろ努力した。でも、あまりうまくいっていない…。それは辛いことですよね。
こんなときは、もしかしたら、原因がほかにあるかもしれません。
そのひとつは自分と相手の情報の受け取り方や、やる気の出る言葉が違うので、どこかで食い違っていることです。
心理学の研究では、何かを伝えるときは、まずは相手が受け取りやすいように言葉がけをした方がよいことがわかっています。
札幌でWebディレクターをしている、白藤沙織(しらふじさおり)です。
私は30年以上企業で働いてきて、人間関係やマネジメントに試行錯誤をしてきました。
そんな経験から、すべての働く人が笑顔になれることを目指して発信をしています。
私は会社に勤めている時代、リーダーとしてスタッフに上手に説明ができずに一人で考え込むことが多く、「どうして伝わらないんだろう」と悩む日々でした。
それが、「LABプロファイル®」という方法を知って、状況が徐々に変わりました。相手の行動パターンを見て、どんな伝え方をしたらいいのか判断できるようになったのです。
今日は、「LABプロファイル®」で「相手に合わせた説明の準備方法」をお話しします。
これを実践すると、説明上手になること間違いなしです!
相手の言葉から、好みの説明方法を探る

人は自分が好きな人の話は熱心に聞きますが、信頼関係がない場合は話をスルーしてしまう傾向にあります。つまり、伝え方には問題がなくても、聞き手との関係で伝わらない現象が生まれるのです。
そうならないために、まずは相手がどんな人なのか、普段の会話や提出される書類などから探っていきましょう。
私が知っておくとよいと思う、イチオシの方法は「相手に合わせた伝え方」を身につけるための実践的なコミュニケーションの手法「LABプロファイルⓇ(ラブプロファイル)」です。
LABプロファイルⓇは「Language and Behavior Profile」の略で、相手の行動をいかに理解し、推測し、影響を与えられるかを見極めるための手法です。
心理学とNLPの応用で、相手の無意識な言葉づかいから「行動パターン」を読み取り、説明や指示を「刺さる言葉」に変えるのが特徴。
ちょっと難しくなりましたでしょうか?
LABプロファイルⓇを実践すると、指示が通りやすくなり、チームの動きがスムーズになります。
なぜなら、普段の会話や提出物などから部下の「行動パターン」を知り、その人に合った言葉で指示・説明できるようになるので、理解度が激変するからです。
LABプロファイルⓇでは、人の行動を14カテゴリに分けて人の特徴を把握していきます。
ここでは、とくに仕事の現場で使える4カテゴリを紹介します。カテゴリ名は覚える必要はなく、だいたいこんなパターンがあると考えてください。
ここではわかりやすく、カテゴリ別に2パターンを対立するように書いています。実際には、「人のパターンに良し悪しはありません。」
これは覚えておいてくださいね。
すぐに動きたい人 vs 周囲を見てから動く人
●すぐに動きたい人 = 主体・行動型
「これだ」と思ったときに、素早く行動を起こして、あまり状況を分析することなく進んでいける人がいます。このようなパターンを持った人を「主体・行動型」と呼んでいます。
すぐに行動して仕事を片付けることは得意ですが、人が何かを判断したり、行動するのを気長に待つことは得意ではありません。
「とにかくやってみる」「飛び込む」「今すぐに」「実現する」というような言葉を使います。
●周囲をみてから動く人 = 反映・分析型
行動せずに熟考し、分析を始めます。行動する前に、十分に状況を把握したいのです。ですので、ほかの人が行動するのを待ち、時が来たら行動を始めます。このようなパターンを持った人を「反映・分析型」と呼んでいます。
じっくり分析することは得意ですが、なかなか行動しないので周囲がイラつくこともあります。
「考えてみる」「~かもしれない」「~のようだ」というような言葉を使います。
特徴
早く行動したくなるタイプ。決断が速い。
効果的な言葉がけの例
「これ、すぐやってもらえる?」
特徴
周囲を見てから動く。準備に時間が必要。
効果的な言葉がけの例
「ほかの資料も検討してから、進めよう」
目標に向かって進みたい人 vs 問題を避けたい人
●目標に向かって進みたい人 = 目的志向型
目標達成の観点から、物事を考えることが好きな人がいます。このようなパターンを持った人を「目的志向型」と呼んでいます。
目標があることで、モチベーションが上がり、優先順位をつけて物事に取り組むのが得意です。一方で問題点を見つけたり、その対策を考えることには興味がありません。
「利点は」「獲得する」「達成する」「欲しい」というような言葉を使います。
●問題を避けたい人 = 問題回避型
避けた方がいい事態や問題に焦点を当て、解決すべき問題や回避することがあるとモチベーションが高まる人がいます。このようなパターンを持った人を「問題回避型」と呼んでいます。
問題点を見つけるとそこに注力する傾向があるので、目標に注意を向け続けることは難しいです。危機管理か得意な人です。
「~は欲しくない」「避ける」「防ぐ」「修正」というような言葉を使います。
特徴
ゴールに向かって行動したいタイプ。達成感が原動力。
効果的な言葉がけの例
「これをやれば、もっと効率的に仕事ができるよ」
特徴
失敗やトラブルを避けることで動くタイプ。安心が大事。
効果的な言葉がけの例
「この方法なら、クレームを防げます」
自分で判断したい人 vs 他人の意見を参考にしたい人
●自分で判断したい人
物事を判断するときに、たくさんの情報を集めて、自分の価値基準に照らし合わせて、自分で判断することでやる気の高まる人です。このようなパターンを持った人を「内的基準型」と呼んでいます。
自分でやる気を起こすことができる反面、人からの意見や外部からの指示を受け入れることが苦手な場合があります。指示を単なる情報として受け取る傾向があるので、管理しにくい人材になることがあります。
「自分でわかる」「自分で決める」というような言葉をよく使います。
●他人の意見を参考にしたい人
物事を判断するときに、人の意見や外部からの指示を必要とします。このようなパターンを持った人を「外的基準型」と呼んでいます。
モチベーションを維持するために、周りの人の意見や指示、フィードバックを必要な人たちです。単なる情報も指示としてとらえます。誰かが方向性を与えてくれるとやる気が起きます。
「フィードバック」「実証されている」というような言葉をよく使います。
特徴
自分で考えて決めたい人。「納得」が大事。
効果的な言葉がけの例
「あなたはどう思いますか?」
特徴
他人の意見・評価に安心感を持つ人。
効果的な言葉がけの例
「〇〇さんもこの方法で、うまくいってます」
全体をざっくり知りたい人 vs 詳細を知りたい人
相手が物事を大きな枠組みで見ているのか、細かな部分で見ているのかを見極めます。
●全体をざっくり知りたい人
物事の全体像や概要をとらえて仕事を進めることが得意です。思い付きを脈絡なく提案することがあります。このようなパターンを持った人を「全体型」と呼んでいます。
森全体に意識を向けることを好むので、細かなことを長時間きかされるとイライラすることがあります。
「ポイント」「大切なのは」「全体像」というような言葉をよく使います。
●詳細を知りたい人
物事の細かい情報を扱うのが得意です。情報を道筋通りに、ひとひとつ、どれもすべて詳細に扱います。このようなパターンを持った人を「詳細型」と呼んでいます。
森全体よりも、木々の枝葉に意識が集中し、優先順位をつけることが苦手な場合があります。
「まさに」「厳密に」「具体的には」というような言葉をよく使います。
特徴
全体像やゴールが先にないと動けない。
効果的な言葉がけの例
「まず、全体の流れをざっくり説明するね。」
特徴
細かい手順・数字が大事。
効果的な言葉がけの例
「この仕事は3ステップあります。1つ目は…」
あなたご自身はどのタイプ?
人にはそれぞれ情報処理するときの得意なパターンがあること、何となくイメージできましたか?
よかったら、ご自身はどの型を持っているのかも確認してみてください。
はっきり、どちらか選べない場合は、どちらの傾向が強いのかという視点で考えおくとよいです。
この自分が持っている型と、相手の型を照らし合わせて、どの言葉を使うとより効果的か考えてから、話をしてみましょう。
どうやったら相手の型を知ることができるかというと、日頃どんな言葉を使っているのか注意して聞くとよいです。また、報告書などで文章を読んでみても掴めることがありますよ。
たとえば、全体型の人の文章と、詳細型の人の文章を比較してみましょう。
今回のプロジェクト進捗はおおむね順調です。
ステップ1~3は予定通り完了、ステップ4は2日遅れで進行中です。
A社との提携交渉は第2回ミーティングまで終了し、現在NDA締結待ち。
B工程にて人的リソース不足により、4月5日~7日に対応が遅れましたが、4月12日時点で調整済みです。
詳細は以下の一覧表にまとめています(表1参照)。
同じテーマで報告しても、文章の長さが明らかに違います。
また、職場の立場や職種でも相手の傾向がわかることがあります。
たとえば、スタートアップの社長、女性では数少ない社長・経営幹部といった場合は、初めてのことでも決断したり、自ら行動する必要があります。
ですので、自ら率先して動く「主体・行動型」だったり、自分の成果は自分で決める「内的基準型」が多いです。
一方、指示に従って動く会社スタッフは、前例を確認してから動く「反映・分析型」であり、指示があった方が安心する「外的基準型」だったりします。
また、売り上げ目標がある営業職、競技への勝利を問われるスポーツ選手は、「目的志向型」の人が多いです。
一方、問題を見つけたい、避ける能力が問われる、医療職、プログラマ、弁護士などは「問題回避型」の人が多いです。
【成功事例】説明上手になるための私のチャレンジとその後の変化

Before:伝わらない指示に双方がストレス
私が管理職になったばかりの頃、部下への指示がうまく伝わらず悩んでいました。
私のタイプ:
- 主体・行動型:「まずやってみよう」が信条
- 全体型:大枠を示せば動けると思っていた
ある部下のタイプ:
- 反映・分析型:十分な情報がないと不安
- 詳細型:具体的な手順を必要とする
私は「これ、お願いね」と簡潔に伝えるだけで十分だと思っていましたが、部下は「何から始めればいいのか」と困っていたのです。
その結果、私は「なぜすぐ動かないのか」とイライラし、部下は「どう進めればいいのか」と不安を感じる悪循環になっていました。
After:相手のタイプに合わせた指示で成果が向上
LABプロファイル®を学んだ後、私は次のように指示の出し方を変えました:
変更点1:ざっくり伝えずに、明確な構造と手順を示す
変更前:
「ホームページの見出し『〇〇〇』をすべて『△△△』に変更してください」
変更後:
「ホームページの見出しを変更してください。2か所あります。
1. トップページの見出し『〇〇〇』を『△△△』に変えてください。
2. 同じ文言がリンク先にもあるので、同様に変更してください。」
変更点2:自由度と安心感を両立するように考えた
基本的な手順は以上です。レイアウトは、お任せします。
迷ったら途中で、相談してください。
このように伝えると、部下は何をすべきかが明確になり、安心して作業に取り組めるようになりました。
また、私も最初にしてほしいことを詳しく伝えることで、結果が違うということが少なくなり、結果としてイライラすることが少なくなりました。
もしあなたも同じような経験があれば、相手のタイプを考えてみてくださいね。
まとめ─ テクニックを効果的に使おう
いかがでしたか?
「なぜ、私がしなければならないのか?」と思ってしまうこともあるかもしれません。
私もよくそう思っていたし、正直、今でもイライラすることはあります。
でも、「相手の反応」が、自分の説明の結果なんです。
伝わっていなければ、伝える方法を変えましょう。
相手のタイプを見極めて、伝え方をちょっと変えてみただけで、説明上手になれるって素敵なことではありませんか?
自分も使ってみたいなと思った方は、次の3ステップでぜひチャレンジしてみてください。
【説明上手になるための3ステップ】
✅ 相手がどんな言葉を使っているかを、まず「観察」する
✅ 自分とは違うタイプだったら、「伝え方」を変えてみる
✅ 反応が変わったか、“結果”を見て検証する
このくり返しで、きっと説明上手になれると思います。
この記事の参考文献
「影響言語で人を動かす」 シェリー・ローズ・ベイ (実務教育出版)